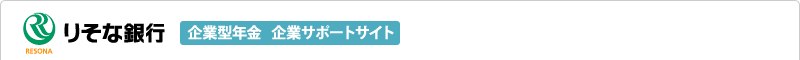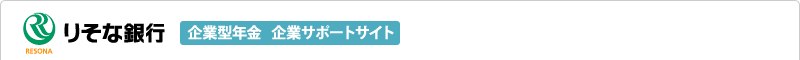企業間異動において、異動元企業と異動先企業の契約番号(JIS&T社管理番号)が同一の場合には、当該加入者の口座番号は変更されません。異動元企業から記録関連運営管理機関(JIS&T社)に制度内企業異動に係る通知を行います。(異動先企業からJIS&T社への通知は特に必要ありません。)
企業間異動において、異動元企業と異動先企業の契約番号(JIS&T社管理番号)が異なる場合には、当該加入者の口座番号は変更されます。異動元企業から記録関連運営管理機関(JIS&T社)に制度内企業異動に係る通知を行い、異動先企業から、制度内企業異動に係る通知に加え、氏名、住所、性別、生年月日等を通知し、口座開設の手続きをとります。
口座番号が変わった加入者に対しては、手続き完了後に「口座開設のお知らせ」、「コールセンターパスワード・インターネットパスワード設定のお知らせ」が送付されます。 |